本は自宅でクリーニングできる!売る前にやっておきたい方法とコツ
本買取では綺麗な物の方が高く売れるため、自分で少しクリーニングするだけでも高価買取に繋がりやすくなります。
ただし、紙製品の本は間違った方法を行うと、シミやページのヨレなどに繋がり、元に戻すのが難しくなるため、正しい方法で行う事が大切です。
今回は、古本屋でも実際に行われている本のクリーニング方法のうち、自宅でも行える簡単なものをご紹介します。
自分でできる!本の基本クリーニング
本のお手入れはホコリ落としから

まずは、保管している間に付着した本のホコリを払い落すことから、クリーニングを開始します。
乾いた綿のタオルで本の表面を拭いた後、本の背(ページが閉じてある部分)を軽くつまんで小口(背と反対側)を下に向け、バサバサと振ってホコリを落とします。
さらに、小口を下に向けた状態で表表紙と裏表紙を軽くたたき、ページの合間に挟まったホコリを取り除きましょう。
ページののど(見開き部分のスキマ)にホコリが溜まっている場合は、100円ショップで売っているエアダスターや刷毛、モップ型の静電気クリーナー、小型ノズルのある掃除機などでこまかくクリーニングを行います。
保管が長かった本は天日干しも必須
長い間ダンボールや本棚にしまいっぱなしにしていた本は、カビの胞子やダニ、本の虫がついていたり、湿気を吸っている可能性があります。
そのため、ホコリ落としを行った後、天気の良い日に1~2日ほど天日干しをしておくとさらに本の状態が良くなります。
ただし、本は紫外線に当たると黄ばんでしてしまうため、直射日光に当たる場所で天日干しをするのは紙を傷める原因になります。
必ず日陰で本を干すようにし、可能であればUVカット効果のある布で本を軽く覆っておくのがベストです。
天日干しをした後は、再度上記のホコリ落とし手順を軽く行い、ダニや虫の死骸を取り除きましょう。
汚れの溜まりやすいカバーはしっかりケアを

本のカバーは直接触れる事もあり、見えなくてもホコリや手垢、唾などでかなり汚れています。
この汚れを落とす方法はいくつかありますが、その中でも手軽にしっかり汚れが落ちる方法を4つご紹介します。
どの方法も水分を使っているため、ツルツルとしているコート紙や、コーティングされているPP紙以外の本では行わないようにしましょう。
また、行う時は必ずカバーを本体から外し、しっかり乾かしてから装着してください。
1.除菌ウェットティッシュで拭く
カバーのお手入れ方法として最も手軽なのが、市販の除菌ウェットティッシュで拭くだけの方法です。
コストもかからず準備もいらないので、それほど汚れが目立たないカバーのクリーニングに最適です。
この際に使用するウェットティッシュは、アルコール入りタイプのものを使うと除菌・消臭効果が高いのでオススメです。
2.花王「かんたんマイペット」で拭く
住居用洗剤として販売されている花王のかんたんマイペットは、壁紙や畳にも使える弱アルカリ性洗剤のため、本カバーのお手入れとしても応用できます。
除菌効果もあり、2度拭きする必要もないため、ドラッグストアやスーパーで購入してしまえば、ウェットティッシュのクリーニング方法とさほど労力は変わらず、自宅でも手軽に行える方法です。
ただし、そのまま使用すると濃度が高いため、「洗剤:水=1:5」の割合で薄めてから使用しましょう。
また、噴霧する時は直接カバーにかけるのではなく、乾いた布に軽く吹き付けてからカバー表面を優しく拭いてください。
ウェットティッシュで拭く方法に比べ、かんたんマイペットの方が汚れ落ちが良く、少々気になる汚れも綺麗に落とせます。
なお、かんたんマイペットでなくても、住居用の弱アルカリ性洗剤なら代用できますが、オレンジの成分が入っていると印刷された油性インクを落としてしまうため、絶対に避けましょう。
3.重曹スプレーを作って拭く
掃除や洗濯に活躍する重曹は、皮脂などの酸性の汚れ落としに強く、本のカバーのクリーニングにピッタリの素材です。
粒子に研磨効果がありますが、硬度が低いためカバーを傷つけにくく、安心して汚れ落としに使用できます。
また、重曹は消臭効果も持っていますので、ニオイが気になる本のクリーニングとしてもオススメの方法です。
市販の重曹小さじ一杯を水100mlで薄め、スプレーボトルに入れて重曹水を作ります。
直接カバーに吹きかけず、乾いた布にスプレーしてから、カバーの汚れを拭き取るだけです。
ただし重曹スプレーは、水分が乾くと溶け残った重曹が出てきてしまい、白い粉が残ってしまうというデメリットがあります。
重曹水を作る時にお湯を使うと、溶け残りが少なくなりますが、もしカバーを拭いた後に重曹が白く浮き出てきてしまったら、除菌ウェットティッシュでサッと拭き取りましょう。
4.セスキ炭酸ソーダスプレーで拭く
重曹の白残りが気になる方や本カバーの汚れが結構ひどいという場合は、少し価格は高くなりますが、セスキ炭酸ソーダを使ってみましょう。
セスキ炭酸ソーダ小さじ一杯を水500mlで薄めてスプレーを作り、重曹スプレーと同様に乾いた布に吹きかけてから、本のカバーを拭いていきます。
セスキ炭酸ソーダは、重曹に比べて水溶性が高いため、乾いた後の粉残りが少なくなり、二度手間を大幅に減らすことができます。
水に溶けやすい分だけ研磨の力は低くなりますが、アルカリ度が重曹に比べて強く、重曹で落とし切れなかった汚れも綺麗にできる可能性がありますので、汚れ落としの効果は心配無用です。
なお、強いアルカリ性になるため手肌への負担も大きくなりますから、必ず手袋をしてクリーニングをしましょう。
【状態別】本のお悩み解決クリーニング
本が水濡れし、シワシワになっている場合
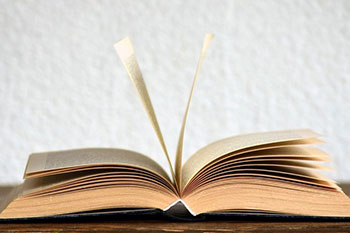
濡れたページの合間にコピー用紙やティッシュペーパーを何枚かはさみ、扇風機(またはドライヤーの冷風)で半乾き状態にしてから、重しを乗せて波を真っすぐにします。
この方法は、日本中の重要な蔵書を扱う国立国会図書館で、実際に水濡れ被害を受けた際に行っている方法です。
また、大手古本買取販売店であるブックオフのコラムでは、濡れた本を冷凍させてから、重しで真っすぐに整えるという方法も効果的だと紹介されていました。
どちらも、本が濡れた状態で行う方法ですので、既に乾いてしまっている場合は軽く湿らせてから行ってみると良いでしょう。
日焼け、汚れでページが黄ばんでいる場合

直射日光の当たる場所で本を保管をしていると、紫外線の影響で紙が黄ばんでしまいます。
また、古い本は酸素や温度の影響を受け続けているため、経年劣化によって黄ばみが発生することもあります。
一度黄ばんでしまった紙は、残念ながら漂白することはできませんが、研磨することで薄くすることは可能です。
ヤスリを使ってページの上部や下部、側面を優しくこすり、黄ばみや汚れの付着した部分を削り落とすという原始的な方法ですが、実はこれが想像以上に綺麗になります。
最初は力の加減などのコツが必要ですので、何冊か試してから、売る前の本に行ってみましょう。
カビによる斑点がついている場合
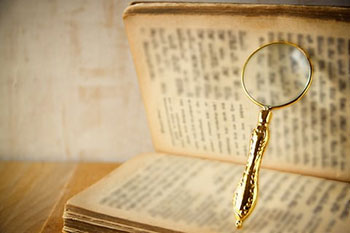
湿気の溜まった場所を好むカビは、押し入れやクローゼットの中で長く保存し続けた本に付着し、汚してしまう事があります。
湿度が高い状態が続くと、カビがどんどん成長してシミをつけるだけでなく、胞子を撒き散らして一緒に保管していた他の本もダメージを受けてしまいます。
まずは、最初にご紹介したホコリ除去・天日干しの手順を行い、しっかりと湿気を飛ばします。
その後、消毒用エタノールを使って本を拭き取り、カビを殺菌しながら汚れを取り除いてきましょう。
この際、紙やインクの種類によっては変色する恐れがあるため、必ず目立たない部分で確認することが重要です。
本にニオイが付着している場合

本を保管している部屋やその近くでタバコを吸ったり香水を使っていると、紙がニオイを吸収してしまいます。
それほど強くないニオイや、付着してすぐの状態であれば、天日干しや換気をしっかり行うだけで取れる事もありますが、それでも取り除けない場合は消臭剤で対応します。
ただし、紙製品である本はスプレータイプの消臭剤が使用できないため、置き型タイプの消臭剤などと一緒に密封し、しばらく放置しておきましょう。
本のニオイ除去には1週間近くかかる場合もありますので、買取前に行う場合は早めに実施しましょう。
値札シールが剥がせない場合

中古の古本を買った場合、本のカバーに値札シールが付けられている事がありますが、粘着剤の種類によっては綺麗に剥がせない事も多くあります。
また、シールをつけたまま長く保管していると、粘着剤が固着して剥がしづらくなる場合もあります。
なかなか剥がせないシールは、ウェットティッシュでこする、ドライヤーの温風をあてる、ライターオイルで浮かせるなど家庭でできる方法もたくさんありますが、実はどれも一長一短なので、安易に行うのはオススメできません。
必ずメリット・デメリットを理解した上で、チャレンジするようにしましょう。